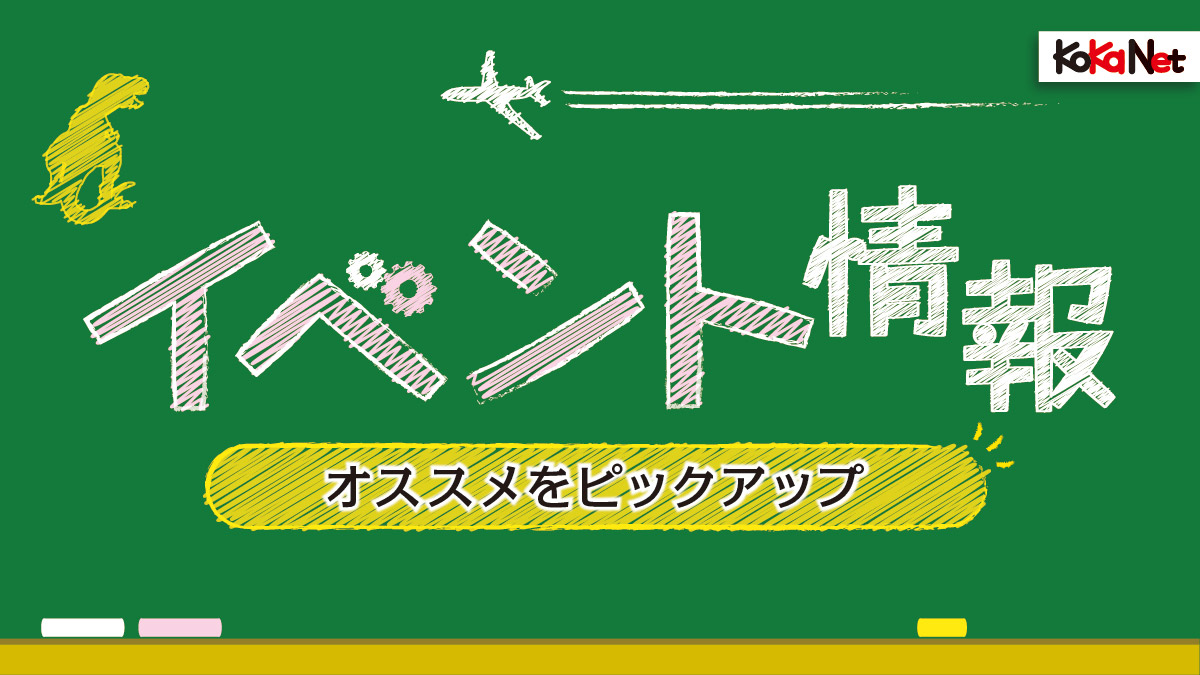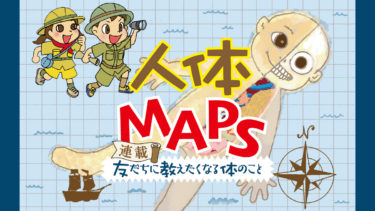『子供の科学2025年5月号』の「ヘルドクターくられ先生のあやしい科学を疑え!」は読んでくれたかな? 本誌では収まりきらなかった、くられ先生の頭の中の徒然考えているお話を、コカネット限定で配信中! 本誌の連載とあわせて楽しんでね。
イラスト/obak(@oobakk)
あの魚もスーパーから……
今回は湿地をめぐる生物多様性の話を本編でしたわけですが、平たくいえば環境問題です。
よく環境問題で、人間が悪なのだから人間がいなければいいという話も出てきますが、これは何も考えていない暴論といえます。
例えば、散らかした部屋は放置しておいても片付きません。当たり前ですが、崩した積み木は誰かが積み直さないと元に戻らないからです。
もちろん、自然はそれなりの再生力があり、人類がいなくなれば急激に自然が回復することはあります。しかし、すでに入り込んだ外来種問題や、ゴミ問題などは、問題自体をなんとかしないと、自然はそれを許容した形で再生するしかなく、その先にあるのは多様性の失われた世界です。
さてさて、この生物多様性、大事なのはなんとなく知ってるけど、水辺の生き物や、ザリガニなんか別にいてもいなくても関係ないじゃないと思う人もいるでしょう。
別にゲンゴロウがいなくなっても、代わりにザリガニがいれば、別に生き物はいるんだから気にしなくてもいいみたいな意見もあります。
もちろん、人間がバランスを崩してしまったものだから、その責任は人間にあるので、バランス回復ができるのも人間しかないので、義務といえば義務なのですが、多様性の維持は何より人間の利益のためでもあります。
例えば、生き物にはさまざまな活用があります。そこら辺で雑草だと思われていたものが、とんでもない病気の特効薬になることも、なんなら庭石に張り付いてたカビから医薬品ができて、臓器移植には欠かせない薬になっていたり、魚のうろこの構造から新しい水着の表面技術が発展したり……。さらには、それぞれの生き物が持つ遺伝子は、まだ人類がどれだけ活用できるかもわかっていないので、その大量の可能性の宝島である多様性を、破壊するのは人類の文明発展にとってもマイナスなわけです。
もちろん、物品だけでなく、湿地の生態系が豊かであれば、そこで生み出される栄養の影響で、川の魚だけでなく、回遊魚や、川の栄養を頼りにしている、ハマグリやアサリといった貝類でさえ、密接につながっています。
よくわからない池の生き物が絶滅するのは、まぁなんか知らないけど気の毒だなぁ……というだけの人も、スーパーに当たり前に並んでいる魚介類、大好きな寿司ネタが1つ、また1つと消えていくのは、よろこぶ人はいないでしょう。実際に、日本のハマグリなどの貝類の漁獲量はもう冗談のレベルで下がっていますし、イカナゴなどは、ほんの2、30年前にはスーパーに普通に並んでいた魚なのに、ここ十年ほどは高級魚になり……そして、おそらくあと何年かで絶滅するといわれています。みんなが大好きなウナギでさえ、稚魚を捕りすぎて、いつまで維持出来るかわからない状態といえます。
都会にいると、イマイチ実感することは難しいのですけど、今現在、日本だけでなく世界中で生物多様性が失われている真っ最中です。
もちろん、原因は湿原の減少だけでなく、さまざまな要因があるのですが、湿地は非常に回復の早い生態系であり、環境の再生に即効性があることでいろいろ期待されており、また最近は庭やベランダに小さなビオトープをつくって自然観察をするというのもブームになりつつあるため、今回取り上げたわけです。
ビオトープは楽しい
悲しい話題を振り返ってるだけでは悲しい気持ちのままですから、前向きに自然を感じるビオトープの楽しさをちょっとお話させてください。
ビオトープというと、広大な敷地に湿地や森林が人工的に用意され、そこに動植物が生態系を……と考える人もいると思いますが、そんな仰々しいものではなくても、コップ1杯に田んぼの土をひとつかみ入れたものを窓辺において観察するだけでも相当楽しいものとなります。
別に田んぼの土でなくても、水辺の近くの土であれば本当にコップひとすくいあれば、そこには自然が潜んでいます。(田んぼや公園の土をもらうときは所有者の許可を得るようにしてください)
例えば、カラッカラに乾いた田んぼの土に、水をいれてそれを窓辺においておくと、暖かいシーズンなら、それこそ2、3日で濁りがとれて、そのあとは、すぐに水草が芽吹き始めます。
小さな芽はぐんぐん大きくなります。また数日たつと、水面近くをピコピコ動くミジンコなども見られるようになります。水草の芽の中にはそのまま育つモノ、枯れるもの、そしていつの間にか水面を越えて成長するものなど、いろいろな生き物が出現します。場合によってはカブトエビなどの大型の生き物も現れるかもしれません。
自分も管理している、ビオトープの池があり。池の底の堆積物がメタンガスを出すようになってきたので、一旦水を抜き、土を入れ替え、中の泥をいったん干して、それを適当な桶にいれたのに、なんとそこからカブトエビが出てきてびっくりした覚えがあります。数年間池の底の泥の中で眠っていたようです。
また、河原の土をビオトープにいれて育てていたら、付近で見慣れない水草が……よくよく調べたら、絶滅危惧種だったみたいな話もあります。そうした生き物が発生してきたら、生き物の名前や暮らしが知りたくなるはずです。
生き物のことを調べている間に、それらの繋がりがわかってくると、ただのキモいウネウネ……ではなく、これはナントカのエサになっていて、これのおかげでナントカは数が抑制されている……みたいな繋がりが見えてきます。そうすると、生物の繋がりが肌間隔でわかってくるので、生き物と自然というものに対しての理解というか解像度がぐっと高まります。水の中にいるなんか小さいやつが、ミジンコにみえて、ミジンコもなんという名前のミジンコなのか、どこの地域種なのか……2、3000円の拡大鏡やスマホの拡大レンズなんかを使って撮影したり観察していくと、ただの土の塊が、生き物の源であることが見えてくるかと思います。
そして、庭につくったビオトープに鳥やカエルがやってきて……と、付近の自然とつながると、またそれは別次元の変化があります。去年、わが家のビオトープにはついに小さな水鳥がきました。
……メダカは全部食べられてしまいましたが。
そういうこともあります(笑)
ともあれ、小さな桶1つからでも始められるので、ぜひともみなさん一度ビオトープ遊びしてみてください。


文