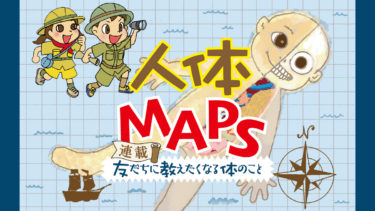『子供の科学2025年3月号』の「ヘルドクターくられ先生のあやしい科学を疑え!」は読んでくれたかな? 本誌では収まりきらなかった、くられ先生の頭の中の徒然考えているお話を、コカネット限定で配信中! 本誌の連載とあわせて楽しんでね。
イラスト/obak(@oobakk)
好きと嫌いなら好きを増やして発信するほうが得
好きと嫌い。
今回のテーマはこの2つを比べて、SNSでの「嫌い」の取り扱いには注意しましょうという話を本紙でしたわけですが、「嫌い」が取り扱い注意なのに対して「好き」は基本的に、率先して発信していくと、結果的にみんな得であるという理論です。
そんな精神論みたいな話……と、鼻で笑う人もいるかもしれませんが、人間という生き物の習性に乗っ取ったもの、ようするに、人間の社会習性をハックして、幸運確率を上げる、幸福度を上げるという理屈にもつながってくるので、ワリとマジなのです。
では、「嫌い」を一切我慢して、「好き」だけを発信していればいいのかというと、おそらくSNSでは、それでもそっちのほうが得なことが多いのですが、私生活でもそんなことをして、「なんでも大好き」、「みんな愛してる」は一周回って、八方美人、事なかれ主義、迎合的だの、しまいには日和見のお調子者とさえ思われてしまいます。実際に、みんなに好かれようとすると、風見鶏のようにクルクルまわって、結局誰にも好かれない……なんて経験ないでしょうか?
そんなわけで、嫌なモノをイヤということ自体は人生をよくしていく上で、それはそれで必要ではあり、SNS上でも上手く使えば、「きちんと意見を持っている人」「矜恃のある人」と、人の評価は上がります。
今の若い世代の人は、生まれたころからSNSがあり、学校ではLINEのグループがあり、ちょっとした失敗もみんなで共有されて笑いものになってしまうこともあるそうで…………そういった社会では、親友をつくるとかより、嫌われないということが最優先になってしまうのは分かる気がします。
そして、風見鶏のようにクルクル廻って、ただただ疲弊する……これがSNS疲れの1つではないかなとも思うわけです。
人間の社会構成の習性を考える
まず、人間の社会というのは1つの生態系に似た構造だといえます。
必ず1つ1つの社会、グループには中心となる人物がいて、それが会社であれば社長なり、学校の生徒会長であり、それらの小さな社会同士がそれぞれ協調したり、争ったりして、循環していくというのが、社会というものです。人間は1人ではあまりに非力であり、すべての学問をすべて理解して専門家になるなんてことは物理的にも不可能です。故に、人はそれぞれの専門性を磨いて、その自分の価値に見合った仕事をするわけです。
この社会感を分析するのは、また別の機会にして、今回はその社会の中での「雰囲気」というものが、生産性にどう影響するか? です。
なんだか難しい話をしてるように思えるかもしれませんが、「勉強しろ 勉強しろ! 宿題が終わるまで部屋から出るな!」といわれるのと、それぞれの得意不得意を調べてみんなで教え合って、みんなでいい点を取ろうとがんばる世界。もちろんどちらも極端ですし、後者が理想的かというと、そうでもないのでしょうが、幸福度は後者のほうが高いでしょう。失敗しても次に生かすために積み重ねますが、前者は激しい罰が待ってそうです。
悪の組織が弱い理由のときにも話をしましたが、恐怖に基づく制御は一時的な秩序をもたらしても、長期的には「心理的コスト」として幸福度を下げ、最近はそういったストレス環境では「業務効率が著しく下がる」ことが知られています。要するにパワハラ人材のいる部署は、そうでない部署より成績が悪いのです。成績が悪いは不幸だわ、不幸のスパイラルです。恐怖での生産性は基本は「ゼロサムゲーム」で、1人が得をする分、他のプレイヤーが損をするので、結果的に全体としては成績が低いという結果とも一致します。
ゲーム理論では「囚人のジレンマ」があります。
互いに協力する選択肢を取ることで、両者が得られる報酬は最大になるという結果です。最近は、多少裏切りを受けて損失が最初多くなっても、それでも協調を増やす方が最終的には強いまであるという研究もあるようです。
こうした生産性や幸福度合いは「感情の伝播」も大きく関わってきます。
難しい話ではなくて、みんなが笑顔だと、自分も自然と笑顔になるよね……というものです。
そういうわけで、みんなが気楽に意見を言い合って、ある程度自由に「良い方向にいく」ことが模索できる組織というのは成功するし、幸福度も高いわけです。
メッチャ難しいですが(笑)
とはいえ、その気分を明るくする方法として「好き」の発信があるわけで、好きの発信を多くすることで、グループ全体の空気感をよくすることができるわけです。
嫌いをベースにするか 好きをベースにするか
結論として、SNSや日常生活において、「嫌い」を基準にした発言や行動は、ネガティブな感情を引き起こしやすく、それが集団全体の雰囲気を悪化させるリスクがあるという話をしました。
一方、「好き」を基準にした発信は、共感やポジティブな感情を呼び起こしやすく、周囲とのつながりを強化し、幸福感や生産性の向上につながりやすい。
「嫌い」をベースにする行動は、一時的にはストレス発散や自己主張の手段として機能するかもしれませんが、長期的には対立を生みやすく、他者からの反発や孤立を招く可能性があります。また、ネガティブな感情は他人にも伝播しやすく、全体の空気が悪化する原因となります。結果として、自分自身もその悪影響を受け、幸福度を下げる要因となるのです。中途半端にネガティブなパワーで成功してしまうと、パワハラ上司が爆誕してしまいます(笑)
とはいえ「好き」だけを全面に押し出すことも現実的ではないでしょう。「嫌い」と感じるものに対して意見を持ち、それを適切な形で伝えることも重要……というのは先にも触れました。単に否定するのではなく、「どこをどう改善すれば良くなるか」、「代替案は何か」といった建設的なアプローチを取ることで、「嫌い」を「改善案」として建設的に利用していくのが勝ち筋です。
敵をつくって、滅ぼすことを目的に生きると、相手の不幸が自分の幸せになります。
推しをつくって、幸せを共有することを目的にすると、相手の幸せが自分の幸せになる。
もちろん、人生はこんな簡単に割り切ることはできませんが、ネガティブなパワーで生きると、人生をハードモードにしかねないので、気持ちだけで難易度を下げることができるなら……ということで、「好き」を発信するほうがお得ではないかと思うわけです。


文